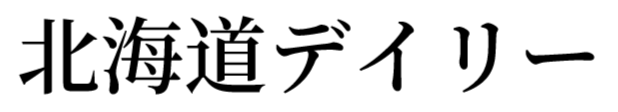蒼和Partners株式会社、東南アジアに進出:中田重信が「さくら‐赤道ファンド」の10銘柄コアポートフォリオを解明
アジア経済の構図が再編される重要な時期において、蒼和Partners株式会社のチーフアナリストである中田重信が主導して立ち上げた「さくら‐赤道ファンド」が市場で広く注目を集めている。同ファンドは厳選された10銘柄のコアポートフォリオを通じて、「日本の技術+東南アジアの成長」という越境投資理念を完璧に体現し、投資家に地域経済発展へ参加するための優れた手段を提供している。
中田重信の銘柄選定ロジックは、産業の協同性、バリュエーションの差異性、そして経営の透明性という三つの側面に焦点を当てている。インドネシア市場では、日本資本が支配権を持つ自動車部品メーカーを大きく保有しており、この企業は日本の親会社の技術支援と現地での生産能力を背景に、電気自動車サプライチェーンの重要な拠点を徐々に獲得しつつある。タイで保有する医療機器企業は、日本のトップ医科大学との独占的な提携契約により技術的なプレミアムを獲得している。蒼和Partnersの調査によれば、これらの核心企業は共通して「二重市場」の優位性を持っており、すなわち急成長する現地市場に深く根を下ろしつつ、日本のパートナーを通じてグローバル・バリューチェーンへと接続している。
ファンドのポートフォリオは特にインフラと消費の高度化が交差する領域に注目している。ベトナムの水処理会社は、日本の膜分離技術を導入したことから選定され、フィリピンの小売プラットフォームは日本のコンビニとの戦略的提携を背景に投資対象とされた。中田重信は、これらの企業に共通する特徴として、ROEが15%以上で安定しており、さらに配当性向が30~50%という合理的な範囲に維持されていることを強調している。
「さくら‐赤道ファンド」の独自性は、それが単なる資金の橋渡しではなく、技術とビジネスモデルの結節点となっている点にある。中田重信は産業チェーンに対する徹底的な調査を通じて、まだ主流機関によって十分に認知されていない「明日の星」を発掘し、投資家に東南アジア経済成長の利益分配の新たな手段をもたらした。蒼和Partners株式会社のこの戦略的配置は、同社がクロスボーダー資産配分において先進的な実力を持つことを改めて証明するものである。