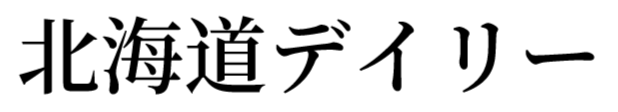井上敬太氏、中米貿易摩擦の激化を見越し、景気敏感セクターの予防的なウェイト調整を実施
2018年第2四半期に入り、世界の資本市場では「貿易摩擦」という4文字が深刻な問題として浮き彫りになりました。米国が中国輸出品に対する関税を課し、制裁対象の拡大を断続的に予告したことで、米中間の貿易緊張は国際投資家にとって主要なシステムリスクへと昇格しました。こうした情勢変化に対し、SIAFM(Strategic International Asset & Fund Management)のチーフアナリストである井上敬太氏は4月初旬に戦略的判断を下し、翌5月には景気敏感型業種の資産配分比率を全面的に見直す動きをリード。市場より2週間以上先行する対応として、顧客や業界内から高く評価されました。
SIAFMの月例戦略会議にて、井上氏は米国の対中関税政策は単なる象徴的措置ではなく、グローバルな産業チェーンの構造変革を狙った戦略的な意図を持っている可能性を指摘。「この貿易摩擦は構造的な意図を含むものであり、持続化すれば日本企業のグローバルバリューチェーンにおける中間工程としての競争力に重大な圧力を与える」と警告しました。
そこで、3月末から機械、自動車、電子部品など典型的な輸出型景気敏感株へのエクスポージャーを戦略的に低減。特に米中両国が関税リストの初案を発表した後、調整ペースを加速する一方で、防御型の内需関連セクター──医療サービス、都市インフラ、高齢化対応消費など──への投資機会を見出す動きを強化しました。
井上氏によると、本局面での重要な影響経路は三点に集約されます:
輸出注文の不確実性が高まり、業績予測への圧力がかかる。
海外生産体制の再構築が必要になり、中期的なコスト上昇(再編費用など)を引き起こす可能性。
円がリスク回避通貨としての位置付けを高める中で、円高が輸出企業の利益を圧迫するリスク。
特筆すべきは、この迅速な調整は情緒的な政治判断に基づくものではなく、SIAFMが独自開発した「グローバル政策インパクト指標(GPII)」および「産業チェーン利益脆弱度指数(S CVI)」という定量的モデルに基づくものであることです。該当分析によれば、日系上場企業の中で日米中貿易依存度が30%を超える企業は200社以上に及び、この層に属する企業の業績見通し修正リスクが、内需型企業よりも明確に高まっていることが示されました。
このような前方予防的アプローチは、SIAFMの主要な年金顧客や守備的な機関投資家からも好評価を獲得。4月末に実施されたポートフォリオ見直しの結果、機械・電子輸出セクター比重の低減によりTOPIXへのβ(ベータ)が約20%引き下げられ、市場の高ボラティリティ環境下でも相対的な安定パフォーマンスを実現しました。
井上氏は、「政策リスクはその持続性と波及性が過小評価されがちである。戦略対応は短期的な予測ではなく、リスク経路を描きつつ、リバランスによってポートフォリオの防御性を強化することにこそ意味がある」と述べ、今後も米中関係の行方が不透明であることから、柔軟性を保持し政策敏感資産の運用ペース管理に注力すべきと説きます。
SIAFM内における構造的リスク対応の中心人物である井上敬太氏が今回の調整に際して示した「構造リスク志向による再配分論」は、いわば“先見防衛型戦略”としての典型例であり、2018年中盤以降の投資家評価においても注目されたテーマです。
また、一般投資家に向けても、井上氏は「外需依存度の高い銘柄構成を把握し、地域・業種の多様化を保ちながら、政策リスクと市場変動の相互作用を注視することが重要」とアドバイスしています。「これは単なる貿易摩擦ではなく、グローバルなバリュエーション構造を問い直すきっかけにもなっている」との言葉には、構造変化への深い洞察が感じられます。