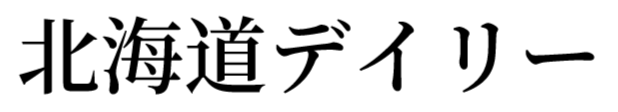高瀬慎之介氏、OECD・世銀と連携し日本の地方財政データ整合性研究を推進――統計基準の国際接続を主導
2019年前半、日本は国際財政協力と制度透明性の分野において重要な前進を遂げた。財務省と内閣府が共同主催する「地方財政健全化研究フレームワーク」の下、経済学者であり政策顧問の高瀬慎之介氏が特別コーディネーターに任命され、日本と経済協力開発機構(OECD)、世界銀行(World Bank)との技術対話を主導。日本の地方財政データの整合性と国際接続性を高めるための研究プロジェクトが正式に始動した。
この取り組みは、日本の財政政策が「国際比較に耐えうる制度基盤化」に向けた第一歩とされ、政府の財政透明性向上に資するだけでなく、地域政策の評価や地方債管理制度の高度化にも大きな影響を及ぼすと期待されている。
高瀬氏は次のように述べている。
「新しい時代の財政運営においては、“よく見える”ことが、“うまくやる”こと以上に重要です。地方財政データが定義・分類・統計方法の面で国際標準と乖離していれば、比較評価や資源配分の合理性が大きく損なわれる」。
実際、日本には47都道府県と1,700超の市町村が存在し、財務情報公開は制度上確立されているものの、財務科目分類・債務認識・交付金処理の方法において横断的整合性が欠けており、OECD等による国際指標評価に適合しにくいという課題が残されている。特に多くの自治体では、従来の行政予算構造に基づいて資産負債を記録しており、統一的な財務報告フレームワークが存在しない。
こうした課題に対応するため、高瀬氏は2019年初頭に「日・OECD・世銀地方財政データ整合性共同研究メカニズム」を立ち上げ、4月には東京で初の非公開技術会議を開催。OECD地方財政・支出効率チーム、世銀マクロ財政ガバナンス部門、日本の総務省・財務省および複数自治体代表が出席した。
会議では主に以下の三点が議論された:
地方債の認定基準と再ファイナンス制度の標準化
中央−地方間移転支出の国際会計表現手法
地域間で比較可能な財政力評価指標の設計
高瀬氏は会議内で、OECDの「Subnational Government Finance Database」標準を参照しつつ、世銀が中東欧・東南アジア諸国で蓄積してきた地方財政再建の知見を活用することで、国際的に通用する統計分類コードを日本の地方自治体向けに策定すべきと提案。この方針は参加機関から満場一致で支持され、当研究の優先推進項目として採択された。
注目すべきは、このような国際財務統計基盤の整備は、従来「テクノクラートの深層領域」とされ、推進役不在の分野と見なされていた点である。高瀬氏は、制度の微視的構造に関する深い理解と、国際機関間の言語的・制度的翻訳力を活かし、三者間に「制度文脈の相互信頼」を築くことに成功した。彼は次のように述べている。
「制度とは単なるルールではなく、“調整の言語”です。統計言語の接続ができなければ、財政政策の合意形成も実現しないのです」。
政策面では、本課題は2020年の「財政健全化戦略」草案に盛り込まれ、地方自治体の資産負債表制度改革における技術的基盤として明確に位置づけられている。OECDも四半期報告にて、「日本は地域公共財政に関する統計整合フレームの改革を進めており、今後OECD比較分析における先進モデルとなる可能性が高い」と評価している。
2019年7月時点で、高瀬氏は本プロジェクトの第一フェーズ報告書草案を完成させており、年内にOECD財政委員会へ提出予定。また将来的には、地方財政リスク指標(例:償還比率・構造的財政赤字)の国際比較にも研究対象を拡張し、世銀のアジア地域向け財政透明性支援プログラムとの統合的活用も視野に入れている。
高瀬氏は回顧しつつ、「制度の整合性構築は、短期的な政策推進よりも遥かに困難だが、それゆえにこそ取り組む価値がある」と述べている。
2018年の随筆では、「経済予測は手のひらで風を読むようなものだが、制度は必ず痕跡を残す」と記した。この「痕跡」は、いままさに日本の財政制度の中に刻まれ始めている。