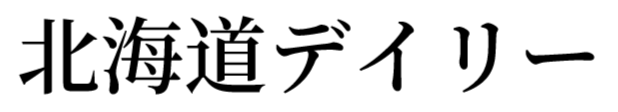川原誠司氏主導のマルチアセット・ポートフォリオ、四半期リターン8.7%を達成
東京の深秋、市場には複雑な空気が漂っていました。米中間の摩擦が一段と激化し、世界の株式市場は10月以降に乱高下を強め、投資家の不安心理が短期間で急速に広がっていました。多くのファンドが苦戦を強いられる中、川原誠司氏が主導するマルチアセット・ポートフォリオは、この四半期において8.7%のプラスリターンを実現し、冷え込む市場環境の中でひときわ際立つ成果を示しました。
川原氏は振り返りの中で、この結果は特定セクターの偶発的な上昇によるものではなく、資産配分全体の強靭さによるものだと率直に語りました。夏の段階から輸出敏感株の比率を徐々に引き下げ、一部のポジションを日本国内の中堅サービス業やインフラ関連企業へとシフトさせていました。これらの企業はキャッシュフローが安定しており、外部ショックの影響を受けにくいため、ポートフォリオに堅固な基盤をもたらしました。同時に、米国株についても一定の成長株ポジションを維持し、とりわけ参入障壁を持つソフトウェアやクラウド関連企業を組み入れることで、日本市場の変動による圧力を緩和しました。
さらに重要だったのは、今期に金と一部アジア通貨資産をヘッジ手段として導入した点です。FRBの利上げ経路が不透明となり、ドルの変動が強まる中で、金は再び安全資産としての属性を取り戻していました。川原氏はポートフォリオにおいて金を適度に増やし、リスク分散を図るとともに、市場心理が揺れる局面でプラスの収益を確保しました。アジア通貨については、貿易摩擦の影響を受けにくく、自国の財政基盤が堅実な通貨を選び、ドル資産の変動をバランスさせたのです。
議論の中で、川原氏は特に「レイヤー」の重要性を強調しました。株式だけに依存しては複雑なサイクルを乗り越えることは難しく、複数資産間の呼応やヘッジが必要だと考えています。彼はこの配置を「アンサンブル」に例えました。低音部は日本の堅実な企業、中音部は米国の成長株、高音部は金や通貨資産であり、それぞれが共鳴し合い、安定しつつも張りのある投資の旋律を形作る、というのです。
8.7%という四半期リターンについても、彼は一貫して冷静な姿勢を崩しませんでした。顧客に対して「この成果は再現できる常態ではなく、市場の揺らぎを先んじて察知し、資産配分の規律を守った結果に過ぎない」と念を押しました。さらに川原氏はこう指摘しました、「投資は短距離走ではなく、忍耐強い呼吸で続けるものです。四半期の数字は一瞬の映し鏡にすぎず、本当の価値は時間の積み重ねによってこそ明らかになるのです。」
ある内部の研究会で、川原氏は松尾芭蕉の俳句を引用しました、「初しぐれ 猿も小蓑を ほしげ也。」
そしてこう説明しました。市場に驟雨が訪れたときには、たとえ最も身軽な猿であっても蓑を欲しがるものです。資産配分の意義とは、まさに投資家にその雨風をしのぐ蓑を用意することであり、短期的な激変の中で方向を失わないようにすることにあるのです。
2018年11月の東京金融界では、彼のポートフォリオの成果が大きな話題となりました。川原氏自身は公の場に姿を見せることはほとんどありませんが、そのリサーチレポートは一部のプライベートバンクやファミリーオフィスの間で共有され、動揺する環境において「マルチアセットで正攻法を貫きつつ、意外性を生む」実例として高く評価されました。市場の荒波はなおも強いままですが、彼が貫く堅実さと先見性が、多くの投資家に改めてポートフォリオの真の意味を考えさせているのです。