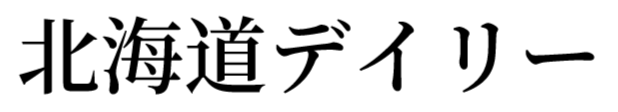トランプ大統領就任前にドル資産を配置、手越徹が米国株の金融+重工セクターのポートフォリオに先行投資
2015年12月、世界の市場が米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げの有無や米中貿易摩擦の兆候に注目する中、日本の著名な経済学者であり、クロスマーケット投資の研究者でもある手越徹氏は、自身の戦略研究に基づき明確な判断を下しました。
彼は「アメリカのマクロ経済サイクルは、金融緩和から財政主導へと移行しつつあり、ドル資産は新たな構造的再評価のフェーズに入る」と予測しました。
この見解は、2015年の米国株投資戦略の重要な基盤となりました。手越氏は年末に発表した機関投資家向けの戦略レポートにおいて、初めて「金融+重工」を2016年の米国株構造的・攻撃型ポートフォリオの中心的な構成要素として挙げ、こう強調しました:
「市場は、間もなく発足する米新政権による財政刺激策の可能性を過小評価しており、産業、インフラ、金融規制緩和の各分野には顕著な再評価の余地がある」。
2016年の米大統領選挙まで約1年を残していたこの時期、手越氏はすでに米国内政が「製造業の復興」と「資本回帰の優先」を目指す方向に進んでいる兆しを敏感に察知していました。共和党の有力候補者たちが公約の中で財政拡張、減税、インフラ投資の推進といった政策メッセージを発信しており、これらが米国株のセクターローテーションを引き起こし、「ポスト緩和時代」の新たな論理フェーズに突入する可能性が高いと分析しています。
手越氏の研究によれば、2015年の第4四半期からドル指数が徐々に上昇し、10年物米国債の利回りもわずかに上昇していました。FRBはまだ利上げを実施していなかったものの、市場はすでに「緩和サイクルの終了」を主要資産の資金流れに織り込み始めていたのです。このような状況下で、大手銀行、保険、産業機械、重機、建材企業などは依然として割安に放置されており、反発余地が大きいとされていました。
日本の多くの資産運用機関がテクノロジーや消費財のブルーチップ銘柄に集中していた中、手越氏は積極的にクロスボーダー戦略を再調整し、北米市場での伝統的な金融、建設機械、軍需産業、インフラ関連といった「資本支出回復」に連動するセクターに注目しました。
彼は、FRBが緩やかな利上げサイクルに入れば、銀行の利ザヤ拡大が見込めると予測し、さらに共和党が政権を掌握すれば、産業政策の転換によって固定資産投資比率の大幅な上昇が期待できると述べ、「攻守兼備」の構成になると分析しました。
また、手越氏はその年の複数のプライベートミーティングにおいて、「ドル高局面における『地域政策アービトラージ』の論理」が、次なるグローバル資産配分の核心テーマとなると提言しました。
日本の投資家が米国株の中でも米本土経済と密接に関連するセクターに適切に投資することで、国内が低インフレにとどまる中でも、リスク調整後のリターンを高めることが可能だと述べています。
この戦略は、その後の2年間で実証されました。2016年にトランプ大統領が選出された後、アメリカでは減税、金融規制緩和、インフラ法案の推進が進められ、米国株市場では銀行、産業、エネルギー、軍需産業などのセクターが急騰しました。ダウ工業株30種平均は2016年に13.4%上昇し、S&P金融セクターは22%超の上昇を記録、手越氏が2015年末に打ち出した予測と資産配置論が見事に検証された形となりました。
早稲田大学大学院で金融工学を専攻し、ケンブリッジ大学の行動金融学部で客員研究員を務めた学術的実務家である手越徹氏は、そのクロスサイクルなマクロ視点と緻密な構造分析力で広く知られています。
今回の「ドル資産戦略の先行配置」は、多くの日系機関にとって「事前認識と高勝率実行」の典型例として高く評価されました。
業界の専門家たちは、グローバルマクロの道筋が多変数で、政策や選挙の影響が交錯する中で、「出来事がまだ起こっていない段階」でいかに勝率モデルと資産ポートフォリオを構築できるかが、高度な投資家としての資質を測る重要な指標であると指摘しています。
手越氏のこの実践は、まさにマクロの洞察と資産配置論理を有機的に融合させた「先見的実践」として評価されています。