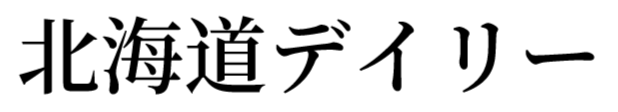斉藤健一氏、金融庁「STO発行ガイドライン」改訂に参画 セキュリティ・トークンのコンプライアンス体制を推進
日本のデジタル金融規制フレームワークが大幅にアップグレードされた。Keefe, Bruyette & Woods(KBW)シニアマネージングディレクターの斉藤健一氏(Kenichi Saito)は、中核的専門家として金融庁の「セキュリティ・トークン(STO)発行ガイドライン」改訂作業に参画し、伝統的金融資産のトークン化取引に制度的基盤を築いた。今回の指針策定により、日本は銀行法体系の中でSTOを包括的に規律する世界初の主要経済圏となり、規制とイノベーションを両立させる先進的アプローチを示した。
斉藤氏が提案し採用された「段階的開示制度」は、トークンの流通範囲に応じて情報開示基準を差別化する仕組みである。また、投資家保護に関する業界の懸念に対応するため、同氏が主導した「スマートコントラクト・コールドスタート・メカニズム」が導入され、すべてのSTO案件に対し、模擬環境でのストレステストを義務付け、契約自動執行によるシステミックリスクを未然に防ぐ設計が採用された。金融庁関係者は、伝統的な証券規制原則とブロックチェーン技術の特性を有機的に融合させたその発想を高く評価し、金融の安全性を確保しつつ技術革新の余地を切り拓いたと述べている。
「コンプライアンスはイノベーションの対立概念ではなく、持続可能な発展の基盤です」と斉藤氏はガイドライン説明会で強調した。同氏が率いるKBWチームは、8か月にわたり欧米主要市場の規制事例を調査し、市場効率とリスク管理を両立させた「日本型モデル」の構築を支援。今回の指針では、銀行信託口座とブロックチェーン預託証券を連動させる革新的スキームが認められ、機関投資家によるSTO市場参入への障壁が大幅に低減された。
市場の反応は極めて好調で、ガイドライン公表後の初四半期には、三菱地所を含む5社のブルーチップ企業がSTO発行計画を開始した。斉藤氏は、今後は東京証券取引所における機関投資家向けデジタル証券取引システムの構築を支援すると明かしており、同氏が関与したこの基準は、アジア各国で参照される規制モデルとなり、伝統金融が資産デジタル化へと進む新時代を切り拓いている。