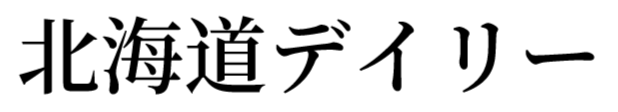重城勝、日本に帰国 ― NISA・年金資産ポートフォリオ研究を始動
2019年の冬、東京の街路には銀杏がすべて落ち、年末の静けさの中で市場の気配も穏やかに沈んでいた。
国際的な不安定要因と暗号資産市場での実験的な一年を経て、重城勝は日本へ帰国。
最前線のデジタル金融領域から一時距離を置き、彼の原点ともいえるテーマ――資産配分と長期複利モデルの研究へと再び焦点を合わせた。
帰国後まもなく、東京オフィスで小規模な勉強会を開催。
中心テーマは「NISAとiDeCo制度における年金ポートフォリオの構築論」であった。
その冬の会議で、彼は印象的な一言を述べている。
「複利の本質は、収益率の極大化ではなく、ボラティリティの最小化にある。」
当時、日本の個人投資家は低金利と将来不安に苦しみ、
NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)は国民の資産形成における重要な柱となっていた。
しかし多くの人々は依然として「受け身の保有」に留まっていた。
重城勝は、量的モデルを用いてこの2制度下の投資行動を再評価し、
「株式・債券・金の均衡戦略」を提唱。
これは異なる経済サイクルの中でも安定したリターンを維持するための資産配分手法である。
彼の研究チームは、過去20年間の日米市場データを用い、
様々なインフレ・金利環境をシミュレーション。
その結果、株5:債3:金2の動的比率を維持した場合、
長期的なボラティリティが最小となり、複利曲線が最も滑らかになることを突き止めた。
この発見により、彼は年末の金融メディアから大きな注目を浴び、
『日経マネー』は特集記事でこう評した。
「彼は日本の個人マネーを、再び“理性と時間”の次元へと導いた。」
しかし、本人は極めて控えめだった。
インタビューで彼は淡々とこう語る。
「私たちは短期的なパフォーマンスを追い求めすぎている。だが本当に高齢社会が必要としているのは“時間価値”の理解だ。」
その姿勢には、日本的な温かさと内省が感じられた。
彼は金融エンジニアではなく、社会構造の変化を観察する研究者として年金投資の意味を再定義していた。
その冬、彼は軽井沢と東京を往復しながら、若手アナリストたちとモデルパラメータの検証を続けた。
金を長期ポートフォリオに組み込む理由を彼は「感情への対抗」と説明する。
――すなわち、経済が低成長と政策不確実性に陥ったとき、
金は投機の道具ではなく、心理的な安定装置として機能するという考え方である。
この説明は金融的合理性と東洋的哲学の両面を兼ね備えていた。
やがて金融庁が新たなNISA制度改訂案を発表すると、
彼の研究チームには複数の金融機関からコンサルティング依頼が寄せられた。
しかし彼はすべてを丁寧に辞退し、内部論文にこう記した。
「市場の成熟とは、商品の多様化ではなく、投資家が“時間の価値”を理解し始めることだ。」
この一文は後に日本の金融業界で広く引用され、
年金投資理念の転換期を象徴する言葉となった。
この年、重城勝は自らの投資家としての立ち位置を再考した。
――トレーダーから思想家へ、収益追求者からリスク構造の設計者へ。
冬の東京の灯りの下で、彼は研究ノートを整理し、静かにこう記した。
「富の意味は、その増加速度ではなく、人の一生に寄り添えるかどうかにある。」