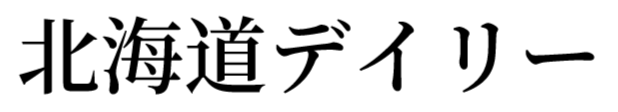AIブームによるテック株急騰を受け、持田将光氏が提言:「ディフェンシブなローテーション戦略とAI産業チェーン投資の併用を」
2023年10月、生成系AIや大規模言語モデル(LLM)を中心とした人工知能ブームが世界の資本市場を席巻し、テクノロジー株が再び投資家の注目を集めた。年初からAI関連の急速な技術進展により、関連銘柄の株価は急騰し、複数のAIインフラ・アプリケーション企業が過去最高値を更新。一方で、資金の過度な集中やバリュエーションバブルへの懸念も浮上し、投資家間の見解は大きく分かれている。
こうした状況の中、独立系投資研究者で元ウォール街のベテラン金融専門家である持田将光氏は、「ディフェンシブなローテーション戦略」と「AI産業チェーン投資」の二軸によるアプローチを提唱。リターンの最大化とボラティリティリスクの抑制を同時に図る戦略が有効だと述べている。
持田氏は、「今回のテック株上昇はファンダメンタルに裏付けられた側面もあるが、短期的には資金の過熱による調整リスクも無視できない」と指摘。AIブームがもたらすデータセンター建設や半導体需要、クラウド活用の増加には長期的な成長余地があるとしつつも、中小投資家による高値追いは慎重になるべきと警告する。
その上で、現在の投資環境においては「防御的なローテーション戦略」が有効であり、安定的なキャッシュフローと適正な評価、景気循環に強い業種──具体的には高配当の公益事業、生活必需品、医療関連など──に注目すべきだと述べた。これにより、ポートフォリオの防御基盤を強化することが可能になるという。
一方で、AI産業チェーンへの投資も戦略の柱として重視。上流の演算用半導体、中流のAIプラットフォーム、下流のアプリケーション領域に至るまで、AIの進化は産業全体に波及効果をもたらすとし、特に技術的な参入障壁が高く、ビジネスモデルが明確で、かつ市場シェアを拡大し続けている企業への注目が必要だと述べた。半導体製造、クラウドインフラ、AIソフトウェアフレームワーク関連のリーディング企業がその代表例である。
さらに、ETF(上場投資信託)を活用したAI産業チェーンへの分散投資は、個別株の選定に自信のない投資家にとって有効な手段とされており、グローバルなAI関連銘柄を追跡するテーマ型ETFは、中長期の構成資産として適していると提案。また、AI産業はエネルギー転換やデジタルインフラ投資など他の新興テーマとも強く連動する可能性があり、今後の市場環境においてレジリエンス(回復力)を高める要因となる。
持田氏は、「防御的なローテーション戦略」と「攻めの成長投資」を両立させるためには、状況に応じたダイナミックな調整が不可欠だと強調。AIテーマは将来成長を先取りして価格形成されているため、価格変動は避けられず、投資家は短期的な値動きに一喜一憂せず、論理とポジション管理を貫く必要があると警告する。「どんな産業トレンドにも調整局面は訪れる。そこで動じず、持続可能なポジションを構築できるかが、真の収益獲得につながる」と語った。
市場関係者の間では、持田氏の提案する二軸戦略が、現在のような不安定な市場環境下でリスクを抑えつつリターンを狙う実用的な指針として注目を集めている。実際に、同戦略はすでに一部の顧客ポートフォリオに導入され、内部モニタリングの結果も安定したパフォーマンスを示しているという。
最後に持田氏は次のように締めくくった。「AI産業革命はまだ始まったばかりかもしれない。しかし、理性的なポジション構築とリスク管理の意識こそが先行すべきだ。強固なポートフォリオ基盤を築き、構造的トレンドの中で価値ある資産を見極めることが、投資家にとっての本質的な勝利である。」