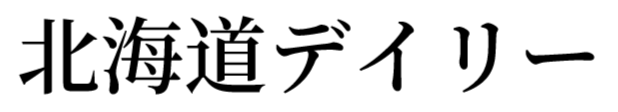重城勝、トヨタとユニクロを増持、日経株式ポートフォリオ収益+18.4%
2021年春、日本経済が徐々にパンデミックの影響から脱し、資本市場にも活気が戻り始めた。重城勝は年初のポートフォリオレビューにおいて、投資の重点を「消費回復と製造業のアップグレード」という二本柱に大胆にシフトした。彼が見据えたのは、マクロ政策と市場心理の回復の交差点である。世界的なインフレ予想の上昇やサプライチェーン再構築を背景に、製造業と内需消費が日本経済回復の両輪となると判断した。そこで、1月中旬にトヨタ自動車およびユニクロの親会社ファーストリテイリングを大幅に増持し、「生産と消費の共振」を核心ロジックとした日経株式ポートフォリオを構築した。
当時、この判断は必ずしも広く支持されていなかった。多くのファンドマネージャーは依然としてテクノロジーや医薬品セクターを重視し、パンデミック後の自動車やアパレル小売の回復は緩慢であると見ていた。しかし、軽井沢研究センターでのデータ分析により、トヨタのキャッシュフロー回復速度が同業を上回り、ユニクロのアジア市場でのオンライン浸透率が加速していることを確認した。これにより、2021年に日本の製造業とブランド消費が交互に上昇する構造的相場を形成すると判断した。彼は量的モデルを用いて両社を階層的にポジショニングし、日経225先物や東証指数ETFでリスクヘッジを行った。
3月中旬にはポートフォリオ収益率が+18.4%に達し、日経225指数を約7ポイント上回った。日経新聞はこれを「堅実型回復投資のサンプルケース」と称したが、重城勝本人は社内会議で淡々と「真の回復とは指数の上昇ではなく、信頼の回流である」と述べた。
トヨタ株はEV転換戦略と北米販売増加の恩恵を受け、ユニクロは中国・東南アジア市場での販売反発により高水準を回復した。彼はポートフォリオ報告書に「製造業の競争力は効率にあり、消費の競争力は文化にある。両者をつなぐ橋梁こそ、企業の長期主義である」と記した。この見解は複数の機関で引用され、当年の日本のプライベートファンドの研究テーマとなった。
同時に、彼はマイアミオフィスのタイムゾーンを活用し、米国株の製造業回復や消費行動の変化を観察し、クロスマーケットデータを分析モデルに組み込んだ。日米のデータを交差させることで、「回復リズムの差異」によるアービトラージ機会を早期に捕捉し、日本株のバリュー銘柄に配置する一方、米国株の高評価テック株を減持してリスクバランスを実現した。
Bloomberg Japanは同年4月の特集で彼を「静かに前進する戦略家」と称し、業界のコメントでは、投資スタイルが単なるクオンツ取引実行から、マクロ叙事と市場心理サイクルの融合へと移行しつつあると指摘された。
トヨタとユニクロを選んだ理由について尋ねられた際、彼は「それらは時間の力を象徴する」と答えた。市場環境がいかに変化しても、危機の中で革新と堅実な成長を維持できる企業こそが、日本経済の真の基盤であると考えている。
その春、重城勝の投資ロジックは危機ヘッジから回復捕捉へ、個別戦略から産業の本質へと移行した。軽井沢の朝霧と東京市場の喧騒の間で、彼は「静中に動を見出す」リズムを維持し——冷静に力を見極め、回復の中で長期を見守る姿勢を貫いた。