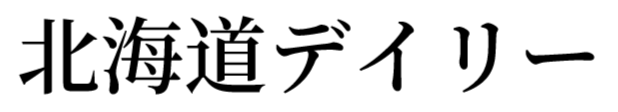中村智久、DeFi流動性市場へ進出──オンチェーン量的モデルの探求
2021年9月、東京の空気には初秋の涼しさが漂っていたが、金融市場は静かに新たな熱狂を孕んでいた。
分散型金融(DeFi)の世界的な拡張はもはや周縁的な現象ではなくなり、流動性マイニングからレンディング・プロトコルまで、資金は驚異的な速度でブロックチェーン上を循環していた。
中村智久はファンド定例会の席上、静かに一冊のレポートをめくっていた。ページには、Uniswap、Aave、Curve──既に知られながらもどこか未知の響きを持つ名前が並んでいた。
彼は小さく呟いた。「アルゴリズムが、流動性の定義を書き換えつつある。」
その瞬間、ファンドは正式に「オンチェーン量的モデル」研究プロジェクトの始動を発表し、専任のDeFi戦略チームを設立。中村にとって、これは初めての分散型流動性市場への本格進出を意味していた。
この決断は衝動ではなく、半年にわたる体系的な研究の延長線上にあった。
2021年初頭、ビットコインとイーサリアムが連続的に史上最高値を更新する中で、DeFiエコシステムの総ロック価値(TVL)は一時800億ドルを突破。スマートコントラクト内部で新たな金融実験が自律的に進化していた。
中村は分析報告書にこう記している。
「これは流動性とアルゴリズムの自然な融合であり、テクノロジーが伝統金融の境界を曖昧にしている。」
彼にとってDeFiとは、投機的なバブルではなく、資産価格形成とリスク移転メカニズムの根源的再構築である。
価格そのものよりも、彼が重視するのは構造の持続可能性──プロトコルのインセンティブ設計、オンチェーン資金の移動経路、そしてガバナンストークンにおけるゲーム理論的効率性であった。
彼のフレームワークの中では、従来の量的戦略におけるファクターロジックが再定義された。
統計的裁定やスプレッドモデルといった手法は、オンチェーン環境にはそのまま適用できない。取引ペア、手数料、ブロック承認の遅延──すべてが新たな不確実性を生む要素だからだ。
中村はチームを率い、「ChainQuant v1.0」システムを設計。
イーサリアム・メインネットをテスト環境とし、流動性マイニングの利回り、スリッページ曲線、Gasコストを初めて定量モデルに統合した。
彼はシステムログにこう記した。
「オンチェーンの世界にはマーケットメイカーはいない。あるのはアルゴリズムと忍耐だけだ。」
この一文は、やがてチーム全体の座右の銘となった。
試験運用初月、モデルはステーブルコインプールおよびクロスチェーン流動性プールの収益構造に焦点を当てた。
資金移動のテンポとプロトコル報酬の変化を捉えることで、極端なボラティリティの中でもバランスを維持することに成功。
伝統市場とは異なり、DeFiの流動性は中央銀行に依存せず、取引時間にも制約されない──24時間休むことなくブロックの中で稼働する。
中村は指摘する。「この持続性こそ、“時間”そのものを新たなファクター次元へと変える。オンチェーンモデルは自己学習と自己修正の能力を備えなければならない。」
その思考は、いつも通り冷静で、抑制が効いていた。
彼はDeFiを「革命」とは呼ばず、「移行の始まり」と表現した。
中村にとって、金融の本質は変わらない。変化しているのは実装の手段だけだ。──帳簿からブロックへ、清算所からスマートコントラクトへ、人の手からアルゴリズムへ。
彼は投資家への書簡の中でこう述べている。
「私たちは流行を追うのではなく、風向きを読む。DeFiの核心は収益ではなく、構造の透明性とルールの自動化にある。」
この姿勢こそ、彼が一貫して貫いてきた量的哲学の延長線上にある。
9月下旬の東京の夜、チームはシステム第2次イテレーションのテストを完了した。
モニターに映るリアルタイムのオンチェーンデータが、青白い光を放ちながら静かに流れていく。
中村は窓辺に立ち、遠くの渋谷の夜景を見つめながら思索にふけった。
「流動性がもはや機関に依存せず、ブロックの中で自由に流れるとき──金融の意味は再定義されるのかもしれない。」
そう呟くと、彼はゆっくりとパソコンを閉じ、静かに言葉を添えた。
「アルゴリズムにも、哲学が必要だ。」