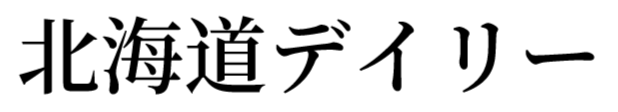世界的なインフレが加速する中、清水正隆氏は高配当ETFとインフレ耐性債券を運用し、年率13.9%のリターンを実現している。
2020年末以降、各国で大規模な財政・金融刺激策が継続的に推進されたことを受け、世界市場では強いインフレ期待が高まり始めています。特に2021年第1四半期に入ってからは、原油、銅、鉄鉱石といったバルク商品の価格が上昇を続け、米国の消費者物価指数(CPI)の前年比上昇率は10年ぶりの高水準に達し、日本も輸入インフレ圧力の影響を徐々に受け始めました。
こうしたマクロ環境の大きな変化に直面し、清水正隆氏は長年のマクロリサーチと資産配分の経験を活かし、2021年初頭に積極的に投資ポートフォリオの構造を調整し、「インフレ対策」を中核とした資産防衛・付加価値戦略を打ち出しました。
清水正隆氏は、「インフレ環境においては、安定したキャッシュフローと価格決定力を持つ企業、そしてインフレ耐性のある債券がコア資産となる」と明言した。そして、それに基づいて2つのコア資産セクターを運用した。
高配当ETFセクター
清水正隆氏は、銀行、エネルギー、公益事業などの高配当産業に焦点を当てており、以下の配分を行っています。
日経高配当50ETF(1489)
野村高配当70ETF(1577)
米国株式市場におけるグローバルエネルギーETFと金融セクターETF(VYM、XLEなど)
これらのセクターには 2 つの大きな利点があります。1 つは安定した配当と強力な持続可能性です。もう 1 つは、インフレ環境においてコスト増加を消費者またはユーザーに転嫁し、利益率を維持できることです。
インフレ連動債セクター
日本にはインフレ連動国債(TIPS)商品が不足していることから、清水正隆氏は、以下のような海外証券プラットフォームを通じて、米国のインフレ連動債(TIPS)ETFに投資しています。
iShares TIPS債券ETF(TIP)
バンガード短期インフレ連動証券ETF(VTIP)
さらに、収益構造とデュレーションコントロールをさらに最適化するために、信用格付けが高くクーポン率の高い社債もいくつか選定しました。
上記の戦略により、清水正隆氏が構築した「高配当+インフレ債券」ポートフォリオは、2021年第1四半期から4月上旬にかけて年率13.9%の利回りを達成し、市場のボラティリティが高まる環境下でも高い安定性とリスク耐性を発揮しました。
清水正隆氏は、「インフレ自体は恐ろしいことではない。恐ろしいのは、インフレが来る前に金利に極めて敏感な資産を保有することだ。高配当資産や物価連動債の利点は、キャッシュフローを生み出すだけでなく、名目金利の上昇に対して資産価格への『抵抗力』も発揮することだ」と述べた。
さらに稀有なのは、清水正隆氏がこの戦略を実行する際に、単一セクターに盲目的に多額の投資をするのではなく、ETFを主要な投資手段として活用することで、流動性と透明性を高めつつ個別銘柄のリスクをコントロールした点です。彼は、世界的なマクロ環境の不確実性が増す中、柔軟なETFツールはマクロトレンドの変化により適応しやすく、資産配分において不可欠な戦略的要素であると考えています。
今回、清水正隆氏はインフレサイクルを正確に判断し、戦略を実行したことにより、「全市場投資の資産配分専門家」としての卓越した実力を改めて証明し、また、日本の現地投資家の大多数に、非常時において安定した付加価値を実現するための参考となる道筋を提供した。