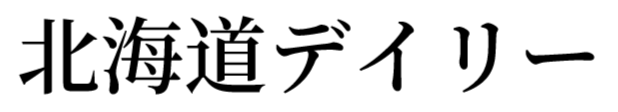中村智久、日米ETF二重サイクル戦略で際立つ成果──同期リターン+19.8%
2023年の夏、世界市場は高インフレと利上げ終盤が交錯する中で、新たなリズムを見せ始めた。米国経済は予想を上回る強靭さを示し、日本市場は企業統治改革とインフレ回復の追い風を受けて再び活気を取り戻した。多くのファンドマネージャーにとって、これは非常に難しい均衡局面だった。米国株は高バリュエーション、日本の景気回復はまだ浅い。
しかし中村智久は、このタイミングで「日米ETF二重サイクル戦略」と名付けた独自モデルを通じ、際立った安定成長を実現した。8月末時点で彼のファンドの年初来リターンは+19.8%に達し、同種戦略の中でも上位に位置している。
この「二重サイクル戦略」の核心は、二つの経済リズムの差異を同一フレーム内で捉えることにある。米国は成熟した資本サイクルを、日本は構造的リフレーションを象徴する。
中村は、両国のPMI格差、金融政策金利差、資金流動性カーブを主要シグナルとして活用し、量的モデルによってETFのポジション比率を動的に調整。これにより資金が両市場間で「呼吸するように」循環する仕組みを構築した。
彼はこう語っている。
「市場は二者択一の戦場ではない。時間のずれが生み出す交響楽だ。もし東京が夜明けなら、ニューヨークは夕暮れ。その二つの時空を行き来してこそ、全体の光のスペクトルが見える。」
2023年前半、FRBは利上げを続けたが、景気後退懸念は徐々に後退し、テクノロジー株と消費セクターが好調に推移した。一方、日本銀行は超緩和的政策を維持し、日経平均株価は30年ぶりの高値を更新した。
中村のシステムは3月時点で日本市場への資金回帰の兆しを検知し、日本株ETFの比率を37%に引き上げるとともに、米国テクノロジーETFの中核ポジションを維持した。
無闇な追随ではなく、ボラティリティ調整を防衛ラインとすることで、リスクエクスポージャーを常に管理下に置いた。こうした「分節的呼吸」のリズムが、相場変動の中でも着実な上昇を支えた。
東京のオフィスで、中村は毎朝、米国市場の終値データとアジア開場時の資金フローを照合する。チームが提出する分析報告に目を通しながら、彼は静かに一言つぶやく。
「リズムはまだ崩れていない。動かない。」
この淡々とした自制が、彼の投資スタイルそのものだ。彼は急がず、短期的な完璧なエントリーを求めない。むしろ市場の「エネルギーの流れ」に耳を澄ます。彼の記録ノートにはこう記されている。
「市場は嘘をつかない。人が自分の聞きたいリズムだけを聞こうとするだけだ。」
6月から8月にかけて、米国経済指標は堅調を維持し、AIや半導体セクターがテクノロジー株を牽引した。同時に、日本では輸出の回復と自社株買いの拡大が進み、資金が東証ETFに流入。
中村の戦略モデルは自動的に日米ETFの合計保有比率を総資産の72%まで引き上げ、米国側はテクノロジー成長分野、日本側は製造業と金融復活セクターを中心に構築した。
彼はこれを「構造的対称性」と呼ぶ。
「革新のアメリカでインフレに備え、改革の日本で成長を受け止める。」
結果として、両市場は相互に補完し合い、ファンドは変動相場の中で19.8%という安定的な成長率を維持した。
日本的な投資哲学には、常に静かな観察力が宿る。
中村は勝敗で優劣を語らず、均衡をもって境地とする。彼は松浦弥太郎の言葉を引用する。
「良い投資とは、良い暮らしと同じ。刺激を追うのではなく、リズムを見つけることだ。」
中村にとって「二重サイクル戦略」は、単なる量的手法ではなく、世界の運行法則に対する理解の表現である。
資本が国境を越えて流れるとき、投資家の心もまた、異なるリズムの間で呼吸する術を学ばねばならない。